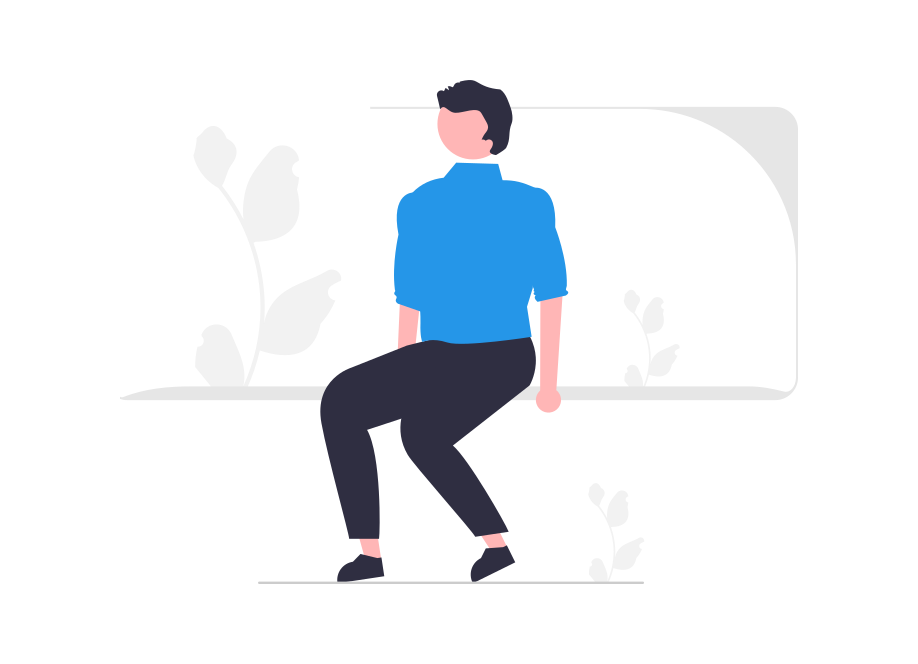5G・6Gは本当に安全?過去の「安全神話」と最新テクノロジーのリスクを徹底解説
私たちが使うテクノロジーって、昔は「安全」と言われていたのに後から危険性が見つかることがあるんですよね。
アスベスト、水銀、DDT、グリホサートなどはその代表例で、当初は便利で安心とされていたのに、後に健康被害や環境リスクが問題になりました[1]。
では、いま急速に普及している5Gや6Gの通信技術はどうなんでしょうか?
現時点では「安全」とされていますが、本当にそう言い切れるのか、過去の歴史と比較しながら見ていきましょう。
過去の「安全評価」が覆った歴史
アスベスト:建材や断熱材に広く使われたが、後に肺がんや中皮腫の原因と判明。 水銀:工業用途や農薬で使われたが、慢性的な神経障害を引き起こすことが判明。 DDT:かつて「夢の殺虫剤」と呼ばれたが、環境汚染や発がん性の懸念から禁止。 グリホサート:除草剤として普及したが、発がん性の可能性が国際機関で指摘されている。
物質名
当初の評価
後の知見・問題点
アスベスト
安全な建材
発がん性が判明し使用禁止へ
水銀
工業に有用
慢性中毒・環境汚染
DDT
画期的殺虫剤
生態系破壊・発がん性
グリホサート
普及した除草剤
発がん性懸念・規制対象
つまり「当時の科学的知見では安全」とされても、長期的なリスクが後から分かるケースは珍しくないのです[1]。
5Gの安全性とリスク
5Gは「高速・大容量・低遅延」で、スマホやIoT、スマートシティに欠かせない基盤になっています。
しかしその一方で、次のような懸念点も指摘されています。
電磁波リスク:現状では人体への明確な健康被害は確認されていないが、長期的なデータは不足している[2][3]。 サイバーセキュリティの脆弱性:接続される機器が爆発的に増えることで、攻撃対象が拡大[4][5]。 「絶対安全」は存在しない:企業や政府は継続的な監視とセキュリティ対策を進めているが、リスクはゼロにはならない[2][4]。
これらの観点から、**「現時点では安全とされるが、将来的なリスクは未確定」**というのが正しい見方といえますね。
6Gの登場と今後の課題
2025年以降に実用化が期待される6Gは、5Gの10倍以上の通信速度を目指して研究が進んでいます。
日本でも実証実験が始まり、信頼性や低遅延性をさらに高める試みが進行中です[6]。
でも、課題もまだまだあります。
実用化初期はセキュリティ検証が不十分な可能性がある。 高周波数帯の利用による人体や環境への長期的影響は未知数。 5G以上に多様なデバイス接続が想定され、サイバー攻撃リスクが拡大する恐れ。
つまり、6Gも「期待」と「リスク」が表裏一体。
本格導入が進むほど、新しい課題が見えてくるはずです[7]。
長期的リスクへの信頼性と評価の重要性
科学技術は「その時点での知見」に基づいて評価されます。
でも歴史が示すように、時間の経過とともにリスク評価が覆る可能性は常にあります。
だからこそ必要なのは――
無条件に信じない姿勢 批判的・検証的な視点 最新情報のアップデートを追うこと
このスタンスこそが、5Gや6Gを安心して使うために欠かせないのです[2][3][4]。
結論:5G・6Gの「安全」をどう考えるべきか
まとめると、
過去のアスベストやDDTのように「当時は安全」とされても後から覆る事例はある。 5Gや6Gは現状「安全」と評価されているが、長期的リスクはまだ証明されていない。 「絶対安全」は存在しない。監視・検証を続けることが健全な姿勢。
つまり、便利さを享受しつつも「安全神話」に依存せず、冷静で科学的な目を持ち続けることが大切なんですね。
情報源(引用)
[1] 環境省「水道水における有害物質の健康影響等に関する文献」
[2] サイバーセキュリティ.com「5Gとは?4Gとの違いやメリットデメリット」

[3] Kaspersky「5Gテクノロジーは安全か?」

[4] Mirait-One「本当に安全? ローカル5Gのセキュリティリスク」

[5] 総務省「5G時代に高まるサイバーセキュリティのリスク」
[6] ソフトバンク「6G実用化に向けた実証実験」

[7] NTT技術ジャーナル「5G evolution & 6Gへの動向」