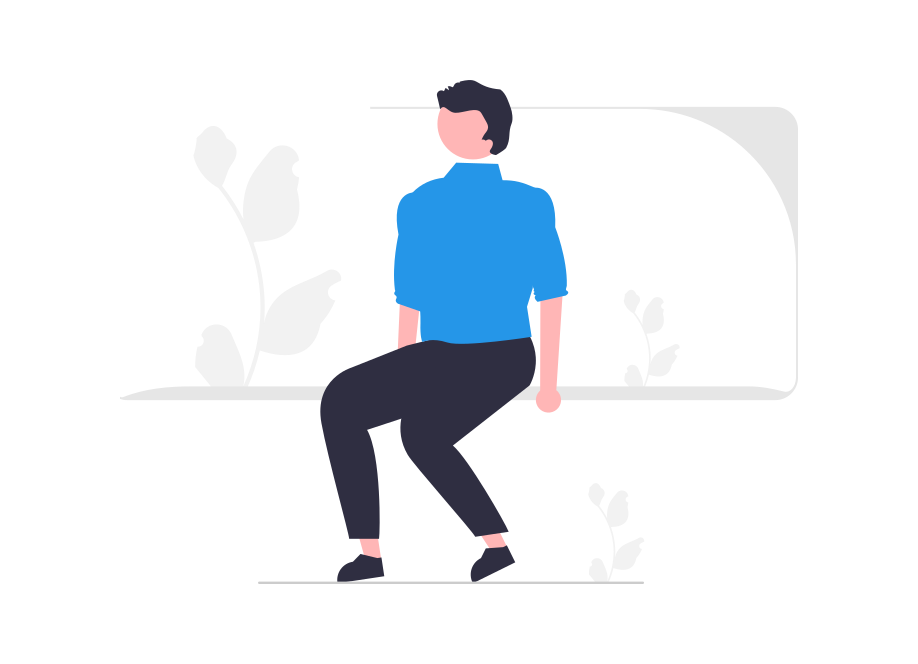🍂四万十町で進む「栗再生プロジェクト」とは?
高知県四万十町では、かつて“栗の名産地”として知られた地域を復活させるために、「しまんと新一次産業株式会社」が立ち上がりました。
同社は「栗の生産」「加工」「販売」までを一貫して行う仕組みを構築し、地域の高齢化で減少した農業の再生を目指しています(しまんと新一次産業株式会社公式サイト)。
もともとこの地域では、年間500トンもの栗が生産されていましたが、今ではわずか30トンほどにまで減少。
原因は、農家の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など。
そこで同社は「四万十の栗再生プロジェクト」を始動し、栗栽培+地域経済の活性化という二つの課題を同時に解決しようとしているのです。
🌰しまんと新一次産業の栗生産と成長戦略
四万十町の栗再生プロジェクトの柱は、「生産」「加工」「販売」の三本立て。
農家や地元企業、行政とも連携しながら、持続可能な農業モデルを構築しています。
■主な取り組みとデータ
項目
内容
過去の生産量
年間約500トン
現在の生産量
約30トン(約90%減少)
主な原因
高齢化・後継者不足・複合作物の減少
加工施設
栗ペーストなどを7か月間製造
投資期間
生産安定まで約8年
期待収益
1ヘクタールあたり約500万円/年
栗の木は植えてから実が安定して収穫できるようになるまで、なんと8年もかかります。
だからこそ、しまんと新一次産業は長期的な視点での投資と信頼関係づくりを重視しているのです(マイナビ農業)。
また、栗をペーストやスイーツ素材として加工することで、**付加価値を高める「6次産業化」**を実現。
これにより「儲かる農業モデル」として注目されています。
🌾耕作放棄地の再生と“限界集落”への希望
四万十町では、耕作放棄地が急増し、地域の存続そのものが課題となっていました。
しかし、しまんと新一次産業はこの“負の遺産”を逆にチャンスと捉え、栗とサツマイモの栽培による土地再生プロジェクトを進めています。
地域おこし協力隊とも連携し、耕作放棄地と借り手をつなぐ活動も展開中(四万十町地域おこし協力隊)。
再生された土地では以下のような効果も。
鳥獣害の減少 景観の保全 若者の定住促進 地域のコミュニティ再生
特に、限界集落と呼ばれる地域でも、農業+加工+販売を組み合わせることで「地域の仕事を生み出す仕組み」が動き出しています。
この動きは、国の地方創生政策とも一致しており、全国からも注目されています(高知県地域アクションプラン)。
💡栗が地域を救う?持続可能な農業モデルとしての可能性
栗は、他の果樹作物に比べて高収益が期待できる作物。
しまんと新一次産業の試算では、1ヘクタールあたり年間500万円の収入が見込めるそうです。
この数字は、同面積の稲作の約5倍にもなります。
高齢化が進む中山間地域でも省力化しやすい栗栽培は、「持続可能な農業」としての強みがあります。
さらに、加工・販売までを地元で完結できるため、地域内でお金が循環する仕組みも整っています(農林水産省 事例集)。
こうした取り組みは、単なる農業の再生にとどまらず、
「地方から日本の農業を変える挑戦」として大きな意味を持っています。
🔗参考・引用元
マイナビ農業「栗農家で億万長者になれる?!」 しまんと新一次産業株式会社 公式サイト 四万十町地域おこし協力隊 – 耕作放棄地の活用 高知県 地域アクションプラン 農林水産省 事例集(四万十地区)
✨まとめ
四万十町の栗再生プロジェクトは、
「高齢化×農業衰退×地方消滅」という3つの課題を同時に解決するモデルとして注目されています。
今後、しまんと新一次産業の挑戦は、地方の農業を変えるヒントになるかもしれませんね。