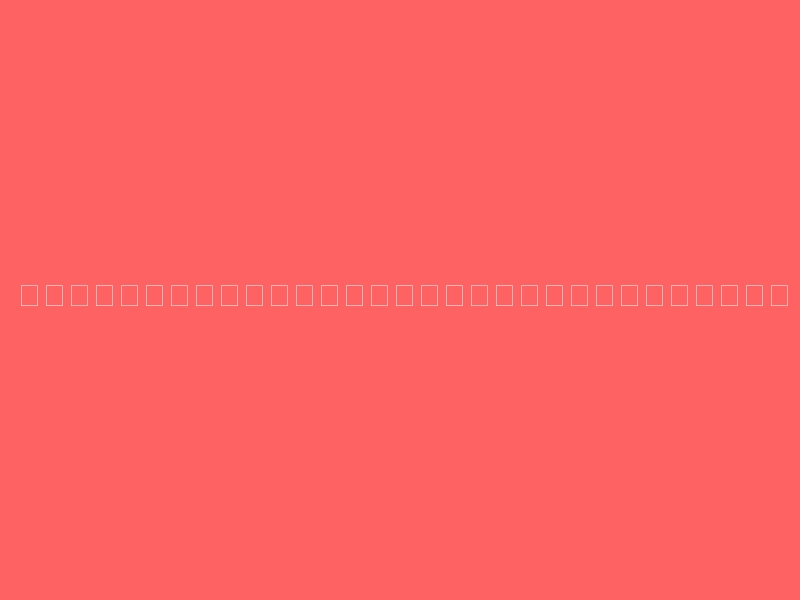大阪府東大阪市で、33歳の女性が元交際相手とされる51歳の男性に刃物で複数回刺され、死亡する事件が発生しました。
この事件で注目されているのは「警察への相談が3年前から続いていたのに、なぜ防げなかったのか」という点です。
ネット上やニュースでは「初動が遅すぎるのでは?」という批判が広がっています。
ここでは、事件の背景や警察対応の課題、そして今後の論点について詳しく解説していきます。
なぜ「初動が遅れた」と言われているのか?
被害女性は数年前から「元交際相手によるストーカー行為や暴力の危険」を警察に相談していました。
しかし、事件発生までに十分な対策が取られなかった可能性があるのです。
日本の警察は「ストーカー規制法」や「DV防止法」に基づいて動きますが、次のような問題があります👇
通報があっても「緊急性があるかどうか」で対応に差が出る 明確な証拠がないと「警告」で終わるケースが多い 加害者側に強制的に踏み込むにはハードルが高い
つまり、被害の相談が続いていても、実際に「命に関わる危険がある」と判断されなければ、警察の動きが鈍くなる傾向があるのです。
この点が「初動が遅い」と批判されている理由になります。
背景にある警察対応の課題
近年、日本では「通報があったのに事件が防げなかった」ケースが相次いでいます。
特にストーカーやDV被害では、次のような課題が浮き彫りになっています。
証拠がなければ「被害が本当にあるのか」判断が難しい 被害者が繰り返し相談しても「現場での保護」につながりにくい 警察のリスク判断基準が地域や担当者によって異なる
実際、警察庁のデータでも「ストーカー相談件数」は年々増えており、2022年には2万件を超えています。
年度
ストーカー相談件数
2020年
19,067件
2021年
20,067件
2022年
21,349件
(参考:警察庁「生活安全局」統計資料)
しかし、事件の防止につながる「保護命令」や「接近禁止命令」まで至るケースは、その一部にとどまっています。
今後の論点と必要な対策
今回の事件をきっかけに、社会では次のような論点が注目されています。
相談内容をどこまで「危険」と判断できるか? 警察がどのタイミングで強制的に介入できるのか? 被害者を守るために「初動対応」をどう改善するか?
たとえば、アメリカではストーカー被害に対して「接近禁止命令」が比較的早い段階で出されるケースが多いと言われています。
一方、日本では「証拠や危険性の明確さ」が求められるため、被害者が守られるまでに時間がかかるのです。
今後は、AIを使った危険度分析や、警察と専門機関の連携を強化することが大きな課題となるでしょう。
まとめ
大阪・東大阪で起きた女性刺殺事件は、警察に相談があったにもかかわらず防げなかったことで、「初動の遅れ」や「対応不足」が強く批判されています。
同じような事件を防ぐためには、警察のリスク判定力を高め、被害者を守る仕組みを早期に整えることが必要です。
私たち一人ひとりが「相談が軽視されない社会」をどう作るかも、これからの大きなテーマになりそうです。
📖 情報源
NHKニュース「大阪・東大阪市 女性刺殺事件」 https://www3.nhk.or.jp/news/ 警察庁「生活安全局ストーカー相談統計」 https://www.npa.go.jp/