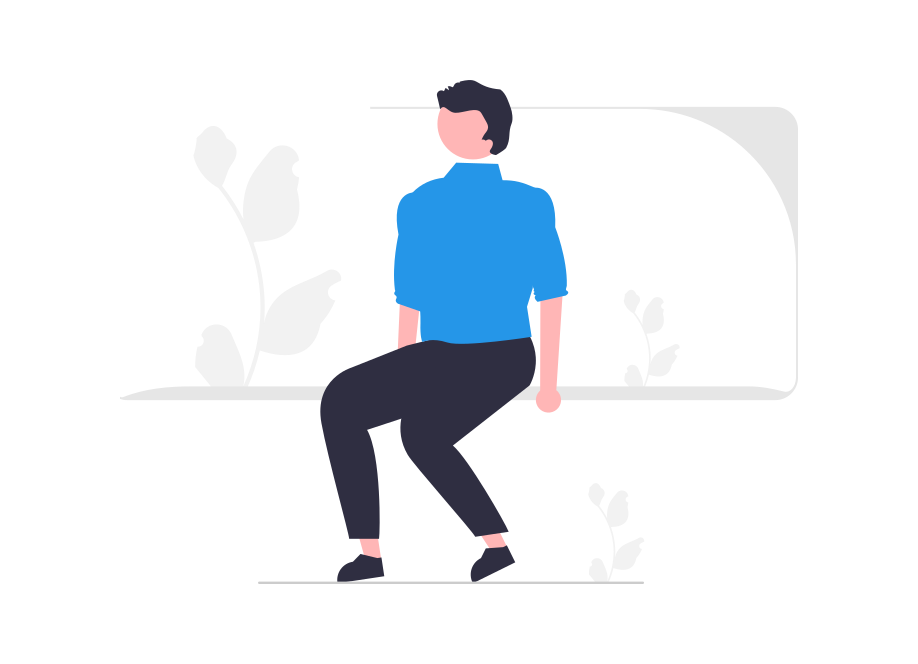小林製薬が通販から撤退した理由とは?紅麹問題と今後の戦略を徹底解説!
紅麹問題による売上急減が直接的な原因
2024年に発生した紅麹サプリメントによる健康被害問題は、小林製薬の通販事業にとって大きな転機となりました。
紅麹問題が表面化したことで、健康被害への不安が一気に広がり、消費者の信頼が大きく低下。
この影響で、自社が展開していたEC(通販サイト)およびコールセンターの売上が急落しました。
具体的には、2022年12月期には84億3000万円あった通販売上高が、2024年にはわずか45億円にまで縮小。
| 年度 | 通販売上高(推定) | |----------------|--------------------| | 2022年12月期 | 84.3億円 | | 2023年12月期 | 60億円前後(推定) | | 2024年12月期 | 45億円 |
この大幅な減収により、通販事業の継続は困難と判断されたようです。
事業ポートフォリオの見直しと構造改革の一環
小林製薬は、紅麹問題の発生以降、経営体制の見直しを本格化。
「選択と集中」を掲げ、通販事業から撤退し、限られた経営資源を新製品の開発や収益性の高い分野に再配分する構造改革を進めています。
その一環として、2025年12月をもって、自社ECサイトおよびコールセンターでの通販事業の終了を決定。
通販終了は「突然の撤退」に見えるかもしれませんが、数年かけて慎重に検討された結果ともいえます。
消費者行動や事業環境の変化も影響
さらに背景には、消費者の購買行動の変化や、競合他社との競争激化も関係しています。
最近では、Amazonや楽天市場などの大手ECモールの存在感が増し、自社ECサイトの運営コストやマーケティング負担が大きくなっていますよね。
加えて、紅麹問題をきっかけに、「小林製薬の商品は安全なのか?」というイメージが広がり、信頼回復には相当な時間とコストがかかると判断されたようです。
こうした外部環境も、撤退の決断を後押しした要因といえるでしょう。
通販撤退の影響と今後の販売チャネル
販売チャネルはどうなる?Amazonなどでの販売へ移行
通販事業そのものは終了しますが、健康食品や化粧品の製品自体は継続販売されます。
今後は以下のチャネルを通じて販売される予定です:
Amazon、楽天市場などの他社ECモール ドラッグストアや量販店などのリアル店舗
つまり、商品自体が手に入らなくなるわけではないので、通販終了=完全終了というわけではありません。
利用者への影響は?一部で不安の声も
長年自社通販を利用していた定期購入者や年配層の顧客の中には、今回の決定に対し「不安」「残念」といった声もあります。
ただし、ネットリテラシーの高い層からは、
「Amazonで買えるならむしろ便利」
というポジティブな意見もあり、移行後の販売チャネルの充実度がカギとなりそうです。
小林製薬への経営的影響と今後の戦略
通販撤退による売上・利益への直接的な影響は「軽微」とされているものの、一部で固定資産の除却損や特別損失の発生が見込まれています。
しかし、そこで浮いたリソースを使って、
新製品の研究・開発 安全性や品質管理の強化 ブランド価値の回復
などに経営資源を再投資していくと発表しています。
紅麹問題によるブランドイメージへの影響と課題
紅麹サプリメントの問題は、単なる一製品の不具合ではなく、小林製薬というブランド全体に対する信頼を大きく揺るがす出来事でした。
ブランドイメージの回復 信頼性の再構築 消費者との丁寧なコミュニケーション
これらが重要になってきます。
まとめ|小林製薬の通販撤退は転換点、今後の成長に注目!
最後に今回の内容を表にまとめてみました。
撤退の理由
今後の対応
紅麹問題による信頼性の低下
信頼回復に向けた戦略を展開
売上の急減
他社ECモール・店舗での販売に移行
経営資源の再配分
新製品・新サービス開発に注力
自社EC運営の難しさ
自社ECから撤退し効率化を図る
今回の撤退はネガティブに捉えられがちですが、今後の飛躍に向けた前向きな一歩とも言えるかもしれません。