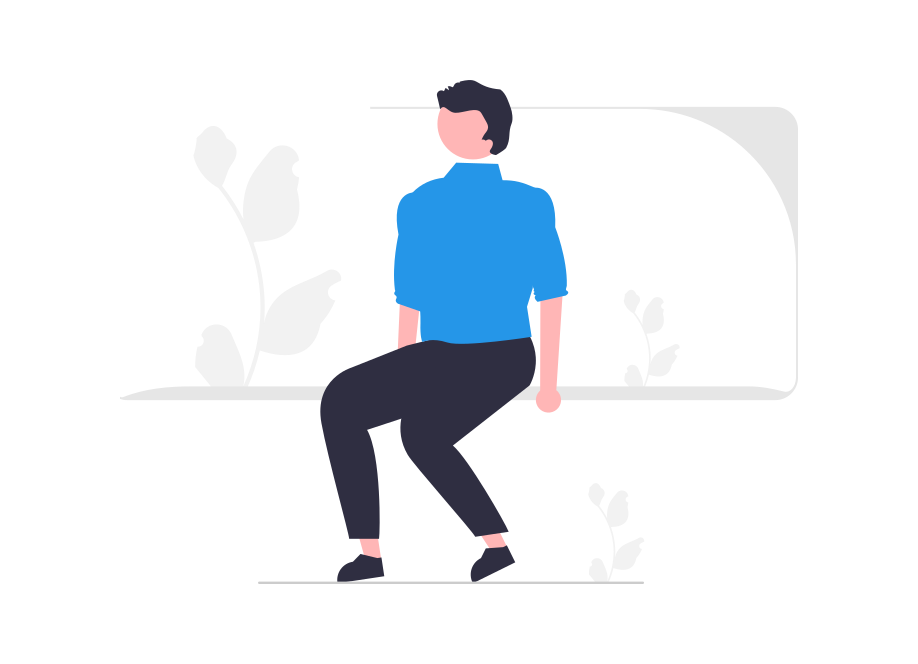「農協(JA)は中抜きばかりしてる」「職員がブラックすぎる」など、ネットや一部報道では農協に対するネガティブな声も見られます。
ですが、本当に農協(JA)は“悪の組織”なのでしょうか?
この記事では、元JA職員の証言や農家の声、農協の実態や仕組みを元に、「農協=悪」というイメージが正しいのかどうかを深掘りしていきます。
JAは“ショッカー”じゃない?元JA職員の見解
元JA職員で、現在は農業経営コンサルタントとして活動している高津佐和宏さんはこう語っています。
「JAを“ショッカー”みたいな悪の組織だと思っているかもしれないが、そんな組織が何十年も続くはずがない。」
実際、JAは地域農家が自ら作った協同組合であり、加入も利用も任意です。
さらにJAには、
「絶対に損しない商売」 「余分に儲ける仕組み」
といった、営利企業のような利益最優先の構造は存在しません。
むしろJAの主な収益源は、農産物の出荷手数料や金融商品のサービス手数料など。中抜きや暴利を得るような仕組みではないのです。
JA(農協)の仕組みと役割とは?株式会社との違い
農協(JA)は、以下のような事業を通じて農家を支えています。
分野
支援内容
販売
農産物の出荷・販路確保
資材
肥料・農薬などの共同購入
金融
貯金、ローン、資金管理
保険
共済(生命・損害保険)
ここがポイントです👇
農家が個人で行うには非効率な業務を、共同で行うことでコストダウンが実現 JAは株式会社ではなく「協同組合」。利益は組合員(=農家)に還元されます
つまり、JAの目的は農家の経営支援であって、収益の最大化ではありません。
とはいえ問題も…JAが抱える課題と批判点
JAが全く問題がない組織かというと、そうではありません。
実際に以下のような課題が指摘されています。
職員の離職率が高い ノルマ(特に共済部門など)が厳しく、精神的・体力的に厳しい現場も。 組織の巨大化・硬直化 組合の規模が大きくなることで、意思決定が遅れたり、現場とのズレが発生。 一部では不祥事も発覚 ごく一部での横領・不正処理なども報道され、JA全体の信頼に影響。
このような背景もあり、「農協の中の人たちも大変」「組織の改革が必要」と感じている職員は少なくありません。
「JAがなくなったら困る」農家のリアルな声
それでも多くの農家にとって、JAは必要不可欠な存在であるのが現実です。
農家の方からはこんな声が上がっています。
「個人で金融や販売を管理するのは無理」 「共同仕入れがあるから資材費が抑えられて助かる」 「地元のJAがあるから農業を続けられている」
つまり、JA=農家のライフラインなんです。
仮にJAが消滅したら、小規模農家は資金調達も物流もままならず、経営を続けることすら困難になるでしょう。
結論:農協は悪ではない。改革の余地はあるが、必要な存在
まとめ
JAは“悪の組織”ではなく、地域の農家が助け合うために作った協同組合 利益を求めすぎず、組合員に還元する仕組みで運営されている 一方で、職場環境や組織構造に課題も残るのは事実 農家の多くは「JAがないと農業が立ち行かない」と実感している
つまり、農協は「完全にクリーンな組織」でも「悪の組織」でもなく、**“課題を抱えつつも必要とされている公共的存在”**といえるでしょう。
💡関連リンク・参考記事
農協は悪の組織ではない 元職員の見解 JAに勤務していた人のリアル体験談 JAの役割と仕組みがわかるYouTube動画