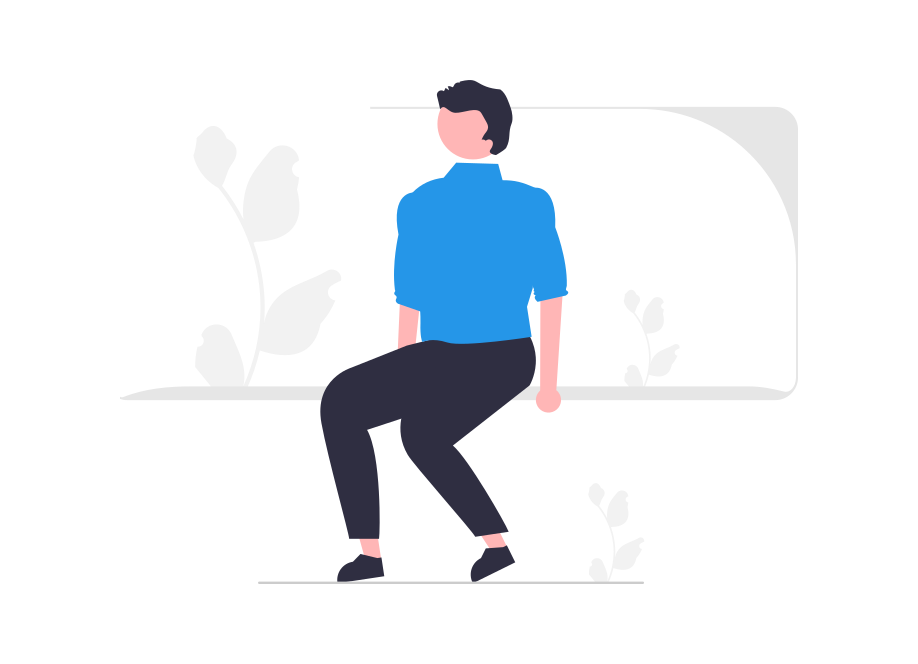環境改変兵器禁止条約(ENMOD条約)は、1976年に国連総会で採択され、1978年に発効した国際条約です。
正式名称は「環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約」。
地震や津波、台風の進路変更など、人工的に自然現象を発生させる技術を軍事的・敵対的目的で利用することを禁止しています。
条約の主な内容
第1条:広範囲・長期的・深刻な影響をもたらす環境改変技術の軍事利用を禁止 有効期限:無期限 罰則規定:なし
この条約は冷戦期の軍事研究に対する国際的な抑止策として生まれ、現在も有効です。
国会で語られた「人工地震技術」 — 浜田和幸政務官の答弁
当時の総務省浜田和幸政務官は国会答弁で次のように発言しました。
「人工地震や気象改変装置については、長年多くの国々が研究開発を進めており、これらの技術は国際的な常識となっている」
つまり、人工地震や気象操作の研究が国際的に行われていることは事実であり、その存在が認知されていることを明言した形です。
ただし、これは「実際に兵器として使用された」という意味ではなく、技術の存在と、それを制限する条約の重要性を説明した発言です。
なぜ人工地震や地震兵器の報道が減ったのか?
1980年代までは新聞や雑誌でも「地震兵器」や「人工地震」に関する記事が散見されました。
しかし1992年以降、このテーマは急速にメディアから姿を消し、1995年の阪神淡路大震災以降は特に報道が激減しました。
報道が控えられる主な理由
デマ・流言飛語扱いの強化 人工地震の話題はオカルトや陰謀論と見なされやすく、科学的議論や災害対応の混乱を避けるため、メディアは積極的に取り上げなくなった。 証拠不足 国会答弁や一部専門家の発言で技術の存在は語られても、「兵器として使用された証拠」が乏しく、ニュースとしての根拠が弱い。 災害報道の優先順位 メディアは復興支援や被害分析を優先し、陰謀論的な話題は避ける傾向が強い。
現在の扱われ方と注意点
現在でもSNSや一部ネットメディアでは「人工地震」や「環境改変兵器」に関する情報が拡散しています。
しかし政府の公式見解や学術的な場では、兵器として実際に使われた事例は確認されていません。
浜田政務官の発言も、あくまで国際規範の説明に留まっています。
まとめ
環境改変兵器禁止条約(ENMOD条約)は1978年発効。人工地震や気象改変の軍事利用を禁止。 国会では人工地震技術が「国際的に存在が認知されている」と説明された。 阪神淡路大震災以降、報道は激減し、現在はネット中心で議論が継続。