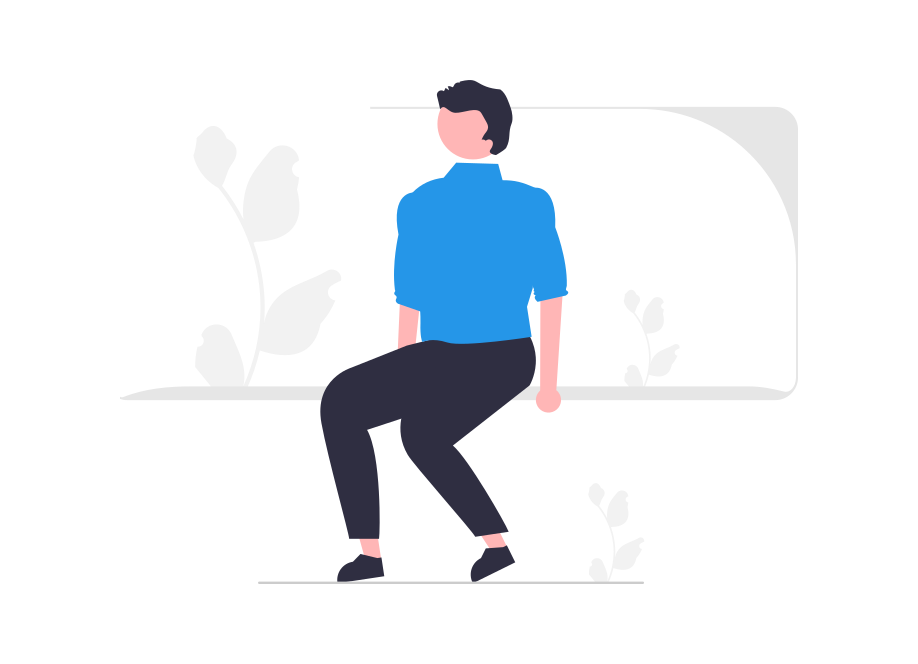はじめに:3,000万円の補助金が話題に!
近年、農業界で注目を集めているのが「農地の巨大区画化(大規模農地整備)」に関する補助金制度です。
農業新聞の報道によると、1件あたり最大3,000万円という大規模な支援が打ち出されました(引用:農業新聞/YouTube)。
一見すると「すごい金額!」「チャンスだ!」と思うかもしれませんよね。
ですが実際のところ、この制度を活用できる農家は限られています。
なぜなら、この補助金が有効に使えるのは地形が平坦で、機械導入がしやすい平野部の農地に偏っているからなんです。
一方で、日本の約7割を占める山間地・中山間地の農家は、この制度をうまく活用できない現状にあります。
つまり、「国の支援制度が一部地域の農家だけを助ける形になっているのでは?」という不公平感が広がっているのです。
巨大区画化とは?目的と狙いを分かりやすく解説
まず「巨大区画化」って何?という方のために簡単に説明しますね。
巨大区画化とは、農地を区画整理して大きな面積にまとめることで、効率的な農業を実現する仕組みのことです。
項目
内容
目的
農地を大きくし、機械化・効率化を進める
メリット
作業時間の短縮・収穫量の安定・人手不足の解消
対象地域
主に平野部(大規模農業がしやすい地域)
支援金額
最大3,000万円/1件
この制度の狙いは、農業の生産性向上と若手就農者の支援です。
大型トラクターやドローンなどの導入も進めやすくなり、「スマート農業」の基盤づくりにつながるとされています。
でも実はこの“スマート化”の流れ、地形に制約のある山間部では実現が難しいんですよね。
平野部に有利、山間地に不利——3,000万円補助の「格差構造」
農業新聞の報道によると、巨大区画化補助金は平野部では効果を発揮していますが、山間地では活用がほとんど進んでいません。
理由は明確で、山間地の農地は小さく分散しているからです。
また、地形が急傾斜しており、大型機械を入れること自体が危険で非現実的な場所も多いのです。
山間地の現実
農地が細かく分かれている 用水路や道路整備に莫大なコストがかかる 区画拡大そのものが物理的に不可能な場所も多い 高齢化で作業負担が増している
このため、補助金の恩恵は**「平野部だけが得をする」構造**になりがち。
山間地では「使いたくても使えない」「そもそも対象外」といった声が多く聞かれます。
実際、農業委員会の担当者も「この制度は平野部モデル。山間地は最初から想定されていない」とコメントしています(出典:農業新聞/YouTube)。
「不平等では?」山間地農家からの声が高まる理由
農家の現場では、補助金制度に対する“温度差”が大きくなっています。
平野部では「補助金を活用して大規模化が進む一方で、山間地では取り残されている」という声が多いのです。
特に中山間地域では、昔から家族経営で細々と続けてきた農家が多く、土地を大きくまとめることがそもそも難しい構造になっています。
こうした地域の農家からは、次のような意見が上がっています👇
「私たちの地域にも使える補助を用意してほしい」 「土地が狭くても続けられるような支援を」 「山間地こそ、補助がないと耕作放棄地が増える」
つまり今、日本の農業政策は“効率化”を重視するあまり、地域の多様性を見失っているとも言えるのです。
政策の偏りが生む「地域格差」問題
農業政策の多くは「大規模化」「効率重視」という方向で設計されています。
それ自体は悪いことではありません。
しかし、全国一律の基準で設計された制度は、地理的条件が異なる地域では機能しにくいのです。
特に中山間地では、以下のような課題が指摘されています。
課題
内容
地形
坂道・段々畑が多く機械導入が困難
労働力
若手が少なく高齢化が進行
コスト
整備費が高く補助金では足りない
生産性
少量多品種で大規模化に不向き
このような地域では、「小規模でも持続可能な農業」こそ支援の方向性であるべきです。
たとえば、観光と組み合わせた「農泊」や、「地産地消」型の販売支援などが現実的な政策になるでしょう。
求められるのは「地域ごとに合った支援」
専門家の間でも、「一律の補助金制度では限界がある」という意見が増えています。
山間地では、ドローンやAIよりも人手の確保や小規模補助が重要という声も多いです。
今後の支援制度には、次のような方向性が求められています。
地形や気候に合わせた“地域別補助”の導入 小規模農家向けの「区画整理なし型」助成 地域コミュニティ単位での維持支援 高齢農家のリタイア支援と若手継承サポート
つまり、「一律の大規模支援」から「地域特化型の柔軟な支援」への転換が必要なんです。
まとめ:農業政策の未来は“多様性”がカギ!
今回の「巨大区画化補助金」によって、日本の農業が抱える構造的な課題が改めて浮き彫りになりました。
平野部には恩恵があるが、山間地では利用困難 大規模化政策が“地域格差”を拡大させる可能性 山間地こそ、きめ細やかな支援が求められている
これからの農業政策に必要なのは、「誰でも使える公平な制度」と「地域の個性を活かす柔軟さ」です。
国が「効率」だけでなく「多様性」も重視できるかどうか。
それが、日本の農業の未来を左右するポイントになっていくでしょう。
📚 引用元
[1] 農業新聞公式チャンネル:「米概算金!あなたの地域と主産地はいくら違う?」「巨大区画化補助の実態」