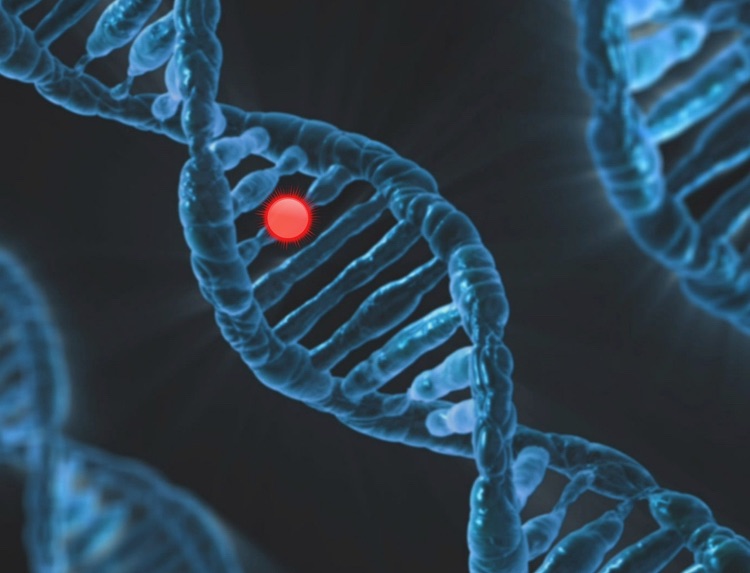日本で「ゲノム編集魚」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
最新のバイオテクノロジーを活用して魚の成長速度や可食部を増やす――。
そんな“未来の食”として注目されていますが、その裏では、安全性や倫理、そして国の補助金の使われ方をめぐって、大きな疑問の声が上がっているのです。
本記事では、リージョナルフィッシュ社を中心としたゲノム編集魚の開発と流通の現状、そして安全性確認や公的支援の問題について、信頼できる情報源をもとに詳しく解説します。
ゲノム編集魚とは?日本だけが進む「安全性審査なし」の市場流通
「ゲノム編集」とは、生物のDNAの一部を“狙って”書き換える技術です。
遺伝子組換えと違い、他の生物の遺伝子を挿入せず、自らの遺伝情報を調整する点が特徴とされています。
日本では2019年から、ゲノム編集を利用した食品の市場流通が始まりました。
しかし、ここで問題なのが――安全性審査が義務づけられていないという点です。
消費者庁によれば、届け出制度は存在するものの、科学的な安全性の確認を行う義務はなく、またゲノム編集食品であることを表示する義務もないのです(読売新聞)。
その結果、スーパーや回転寿司チェーンなどでゲノム編集魚が並んでいても、一般の消費者にはそれを知る手段がほとんどありません。
海外――特にEU諸国では厳格な規制が敷かれ、「安全性確認なしで市場流通することはあり得ない」とまで言われていますが、日本は例外的な緩和国家とされています(Wellness News)。
この違いは、まさに“情報の透明性”という点で大きな隔たりを生んでいるのです。
リージョナルフィッシュ社とは?公的補助金で進むゲノム編集魚の事業拡大
ゲノム編集魚を開発・販売している中心的企業のひとつが、京都大学発のベンチャー「リージョナルフィッシュ株式会社」です。
同社は、マダイやトラフグといった高級魚を対象に、成長を早めたり可食部を増やしたりする技術を開発しています。
例えば、同社が販売する「22世紀鯛」や「高成長トラフグ」は、通常よりも成長が早く、養殖効率が向上するという特徴を持っています(note記事)。
しかし注目すべきは、こうした事業が多額の公的補助金によって支えられているという点です。
支援元
補助内容
金額(公表)
年度
経済産業省・中小企業庁
研究開発助成金
最大9,750万円
令和4年度
NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)
研究開発型スタートアップ支援
約1億円規模
令和3〜5年度
地方自治体・大学連携支援
共同研究費・施設提供
非公開
継続中
つまり、まだ社会的な合意が十分に得られていない技術が、国の資金で大規模に推進されているという現実があります。
これに対して国会内でも、「安全性や倫理面が未検証のまま公金が投入されているのは問題だ」との声が上がっています(日本消費者連盟)。
安全性への懸念:予期せぬ遺伝子変化と生態系リスク
ゲノム編集魚のリスクとして指摘されているのは、「突然変異」や「想定外の遺伝子改変」の可能性です。
実際に一部の研究報告では、満腹でも食べ続けてしまうマダイや、運動能力が低下したトラフグなどの異常行動が報告されています(Facebook投稿・松尾氏)。
このような性質の魚がもし養殖施設から逃げ出した場合、自然界で生態系を乱すリスクも懸念されています。
海外――特にアメリカやカナダでは、こうしたリスクを防ぐため、生きたゲノム編集魚の市場販売自体を厳しく制限しています(Table自然派)。
さらに、死亡魚が大量発生した際の水質汚染リスク、養殖池からの微生物汚染など、環境面での影響も軽視できません。
現時点で日本の制度は「企業の自主判断」に委ねられており、国として明確な基準や検証制度が整っていないのが実情です。
情報公開・対話不足と「言論への圧力」問題
もうひとつ深刻なのが、企業と市民との対話の乏しさです。
市民団体や研究者が「安全性を説明してほしい」と要請しても、企業側が十分な情報を公開していないという指摘があります。
一部では、批判的な発言を行った市民やジャーナリストに対して、**法的な威圧行為(名誉毀損の警告など)**が行われたとの報道も出ています(長周新聞)。
このような状況は、科学技術への信頼を損ねるだけでなく、健全な社会的議論を妨げることにもつながります。
「市民が知る権利」「選ぶ権利」を保障するうえでも、企業と行政はもっとオープンな情報公開を進めるべきではないでしょうか。
ゲノム編集魚の流通は、「食の未来をどうつくるか」という大きなテーマに直結しています。
そのためには、単に技術を推進するだけでなく、社会的合意と科学的検証の両立が必要です。
現状、日本では以下の課題が残されています。
安全性確認の仕組みが不十分 表示義務がないため消費者が選べない 公的補助金が倫理的議論を追い越している 市民との対話・情報公開が遅れている
こうした課題を放置すれば、将来「何が食卓にのっているのか分からない社会」になってしまうかもしれません。
国・企業・消費者が協力し、科学的データに基づいた透明な政策形成を行うこと。
それが、ゲノム編集という新技術を正しく使うための第一歩になるはずです。
まとめ:安全・信頼・情報公開がカギ
リージョナルフィッシュ社が開発・販売するゲノム編集魚は、確かに革新的な技術成果です。
しかし、その一方で、安全性確認が十分でないまま流通が進み、さらに国の補助金によって加速している現状は見過ごせません。
「科学の進歩」と「市民の安全」をどう両立させるのか。
いまこそ、日本社会全体で議論を深める必要があります。
食の安心・安全は、私たち一人ひとりの選択と声から生まれます。
だからこそ――知ること、考えること、そして問い続けることが大切です。
引用・参考文献
ゲノム編集魚流通に膨大な公的支援 安全性未確認のまま全国 リージョナルフィッシュ、経済産業省/中小企業庁の令和4年度助成金情報 回転寿司チェーンへの公開質問状 読売新聞:ゲノム編集食品の届け出制度化から5年 日本消費者連盟:院内集会資料 Table自然派:ゲノム編集魚の養殖問題 長周新聞:「名誉毀損」かざす恫喝報道 Facebook投稿・松尾氏による現場報告