〜高騰と暴落の波に揺れる農家と流通の真実〜
はじめに:米価格の乱高下が止まらない理由
2025年の日本では、米の価格が「急騰」と「急落」を繰り返す異常事態が続いています。
一見すると「高値で売れるなら農家に利益が出るのでは?」と思われがちですが、実際にはまったく逆の現象が起きています。
全国の米農家が疲弊する一方で、卸売業者や中間流通業者だけが利益を拡大している――。
そんな“ねじれた構造”が、いま社会問題として注目されています〔出典:1・2・3〕。
なぜこのような不公平な仕組みが生まれたのか?
そして、私たち消費者や日本の食卓にはどんな影響があるのでしょうか?
ここでは、最新データと専門家の分析をもとに、「米価の裏側」で何が起きているのかを徹底解説します。
米価格の推移と農家の苦境:利益が届かない構造
2025年秋、コメ価格は過去最高水準へ
2025年秋、市販のコメ価格は5キロあたり4,000〜4,500円台に上昇。
前年よりさらに高値となり、消費者にとっても家計負担が重くのしかかっています〔出典:4・5〕。
しかし、驚くべきことに、この「高値」が農家の収入増加にはほとんど結びついていません。
なぜなら、原材料費や農業資材の価格が同時に高騰しており、しかも近年の異常気象による収穫量の減少が農家経営を直撃しているからです〔出典:6〕。
年度
市販価格(5kg)
農家販売価格(玄米60kg換算)
備考
2023年
約3,200円
約9,000円
通常年
2024年
約3,800円
約9,500円
原料費上昇
2025年
約4,300円
約9,200円
資材高・天候不順
※農水省統計・各報道を基に筆者作成
このデータを見ても分かるように、小売価格が上がっても、生産者の販売価格はほとんど変わっていません。
つまり「米価高騰=農家が儲かる」という単純な話ではないのです。
農家の離農・倒産が過去最多に
東京商工リサーチによると、2025年はコメ農家の倒産・休廃業件数が過去最多となっています〔出典:1〕。
「作っても利益が出ない」「資材費が払えない」といった理由で、稲作から撤退する農家が急増しています。
これにより、日本の食料自給の根幹が揺らぎ始めており、地方の過疎化・農地放棄地の拡大にもつながると懸念されています。
中間流通構造と卸売業者の利益:5次問屋の闇
「多重構造」が米価を押し上げている
日本のコメ流通は非常に複雑です。
農家 → JA(農協) → 地方卸 → 広域卸 → 小売卸 → スーパー・飲食店
というように、**最大で5段階もの中間業者(=5次問屋)**が存在しています〔出典:3〕。
それぞれの段階でマージン(中間手数料)が上乗せされるため、消費者価格は高くなる一方で、生産者の取り分は減っていきます。
流通段階
主な役割
マージン率(推定)
農家
生産
–
JA・集荷業者
集荷・保管
約10〜15%
地方卸
精米・ブレンド
約10%
広域卸
物流・在庫調整
約5〜10%
小売卸・小売店
販売
約20%
結果として、最終価格の約4割が中間マージンという試算も出ています。
卸売業者だけが好調
こうした中、2025年には大手卸売業者の一部が過去最高益を記録しました。
特に木徳神糧など大手は、米の価格変動期に在庫を巧みに調整して利益を拡大しており、まるで「価格変動がチャンス」になっている構図です〔出典:2・7〕。
農家が苦しむ裏で、流通側が潤う。
この構造こそが、いま「令和の米騒動」とも呼ばれる混乱の根本原因といえるでしょう。
構造的な課題と消費者への影響
政策対応の遅れと「市場制度疲労」
農林水産省は価格安定を目的に備蓄米を放出していますが、その9割以上がJA全農など特定の流通ルートに偏っており、市場全体への効果は限定的と指摘されています〔出典:8〕。
また、資材高・円安・燃料費上昇など、農業経営を取り巻くコスト環境は悪化の一途です。
専門家の間では「市場制度疲労」という言葉も登場し、戦後から続く農業制度の限界が浮き彫りになっています〔出典:10〕。
消費者にも重い負担
米価が上昇することで、当然ながら消費者の食費にも影響が出ます。
特に低所得世帯では、パンやパスタなど輸入小麦製品に切り替える動きも増え、結果的に「主食の多様化」が進む一方で、国内米の消費量は減少傾向にあります。
これがさらに米価の不安定化を招くという悪循環です。
政策の課題と今後の展望:流通の透明化がカギ
「中間コストの見える化」が必要
経済アナリストの鈴木宣弘氏は、著書『令和の米騒動』の中で「中間マージンの透明化と、生産者へ利益を還元する仕組みづくりが急務」と指摘しています〔出典:6〕。
さらに、京都新聞の特集では「ちょうど良い価格」を目指す政策、つまり生産者と消費者双方が無理のない価格で取引できる制度設計が重要だとしています〔出典:12〕。
政策提案
期待される効果
中間業者の取引情報公開
マージンの適正化
備蓄米の販売経路多様化
市場価格の安定化
民間備蓄の拡大
財政負担の軽減・リスク分散
農家への直接補助制度
離農の抑止・生産意欲の維持
財務省も2025年秋に「民間備蓄の活用による安定供給」を提案しており、国の仕組みそのものが見直され始めています〔出典:20〕。
まとめ:日本の米を守るためにいま必要なこと
2025年の米価高騰は単なる市場変動ではなく、制度疲労と流通の歪みが重なった構造的な危機です。
農家の努力が報われず、中間業者が利益を独占する構造を放置すれば、近い将来「日本産米が買えない時代」が来るかもしれません。
消費者としては、「安い米を探す」だけでなく、「どこから買うか」「誰を支えるか」を意識することも重要です。
また、国や自治体が、流通の透明化と農家支援を両立させる政策を実現できるかどうか――そこに日本の食の未来がかかっています。
参考・引用元一覧
[1] コメ農家の倒産・休廃業が過去最多 ~ コメ作りの「あきらめ」

[2] コメ卸売業者が過去最高の売上を記録 – note

[3] 米の「5次問屋」どこに? 流通のせいで高騰? – JAcom

[4] 『令和の米騒動』(鈴木宣弘) | 文春オンライン

[5] 【令和コメ騒動】新米流通で高止まりコメ価格…

[6] 鈴木宣弘氏 緊急提言『令和の米騒動 食糧敗戦はなぜ起きたのか』

[7] 【異例の声明】木徳神糧「コメの市場価格をつり上げた…」

[8] 「小泉備蓄米」問題化の兆し – PRESIDENT Online

[10] 米価高騰と制度疲労の構造的連関 – note
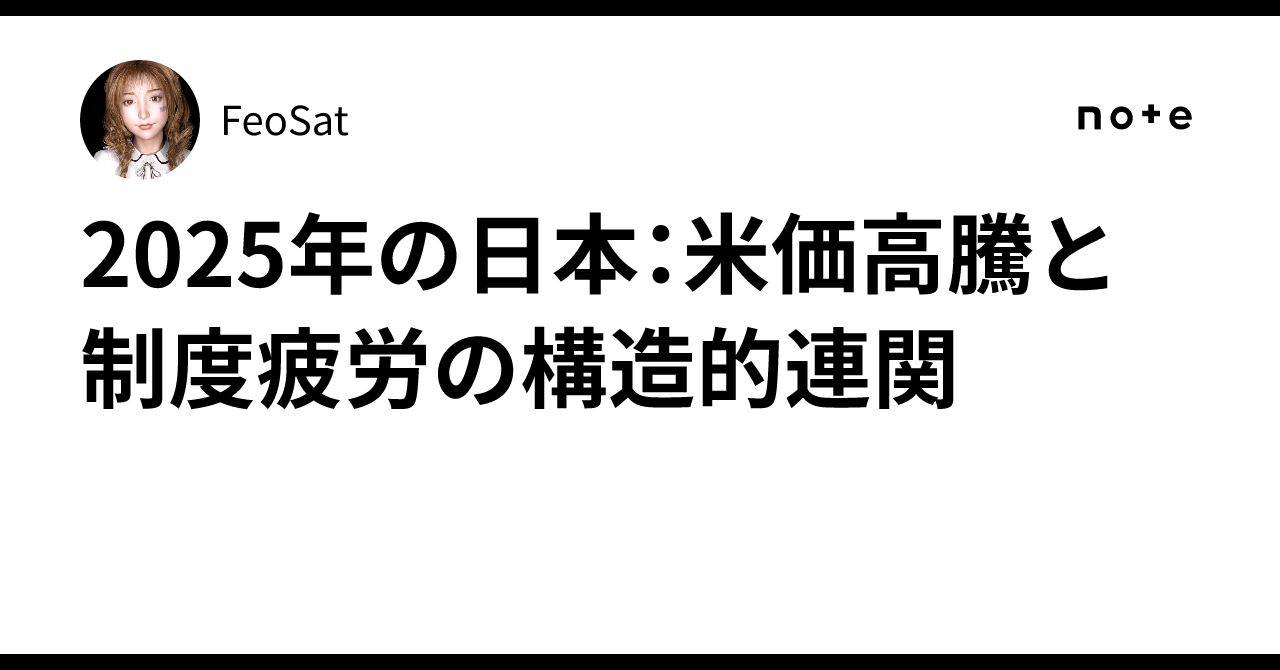
[12] コメ価格安定のカギは「ちょうど良い価格」 – 京都新聞

[20] 財務省「民間備蓄の活用」提案 – 読売新聞

✅ この記事のポイント
米価の乱高下の背景には「5次問屋構造」と「制度疲労」がある 農家はコスト高と天候不順で経営悪化 卸売業者は過去最高益を記録 政府は備蓄米・流通改革を急ぐ必要 消費者も「誰を支えるか」を意識する時代へ

